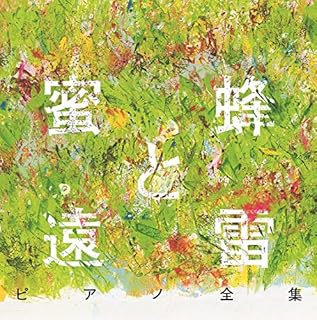第156回直木賞を受賞した本書。話題になっていたのは知っていましたが、いろいろ忙しくて読む暇がなく、ダンロードはしたけども、本棚の隅っこに埋もれていました。先日、たまたま手元に本がない時があったのでスマホで読み始めて、2日で読み切りました。
電子書籍だと、どれだけの積読(つんどく)してあるのかわからないから怖いですね。ただ、こうやって、ふと思いついた時に、気軽に読み始めることが出来るようになったのはありがたいです。荷物も嵩張らないし。
書評というか読んだ感想
1日目でだいたい半分、二次予選の結果発表まで読み切りました。
ここまで読んだ時の感想は、間違いなく傑作のひと言です。4人の主人公を中心とした群像劇になっていますが、キチンと登場人物ごとの書き分けが出来ているしとても読みやすい。主人公の1人である明石が一次予選を突破した時は思わず僕も嬉しくなりましたし、2次予選の時はポカンとしてしまいました。
2日目で読み終わった時は、なんとも締まらない印象を受けました。
明石が抜けた後、「蜜蜂と遠雷」は天才たちの馴れ合いの物語となってしまいます。そこまで広がりを見せていた世界が急に狭くなった印象を受けました。三次予選での塵の演奏前でのホフマン先生との対話から、もう1段階の広がりを見せるかと思ったら、そこまで行かずに終わってしまった。
”音楽コンクールをそのまま、最初から本選までのすべてを小説として書く”という作者の気持ちは伝わってきましたが、物語としては、予定調和のままに終わってしまったという印象があります。
花火大会で、最後の花火がしょぼくて「え、これで終わり」みたいなやるせなさ。コンサートなら最初の小品が良かった一方で、期待が膨らんだメイン・プログラムで失敗してしまったような感じ。
天才たち”だけ”の物語
天才の物語と言うと、漫画家の曽田正人先生をイメージします。「シャカリキ」「昴」「MOON -昴 ソリチュードスタンディング-」「CAPETA」といった数々の天才の話を描いた彼と同様の臭いみたいなものを、僕は物語から読み取りました。(ちなみに初めて読んだ曽田先生の作品は「め組の大吾」落合先生がステキだった)
曽田先生の描く天才たちは、孤独に陥ります。「シャカリキ」の主人公である野々村輝は、ロードレースに熱中し、ついには高校を退学して単身ヨーロッパに向かいます。「昴」「MOON -昴 ソリチュードスタンディング-」の主人公の宮本昴も、溢れんばかりの才能と自尊心故に、バレエ団を転々とします
天才の物語は、究極的には周りからの羨望と、究極的には拒絶にあると僕は思います。
まわりが理解できないことを平然とやってしまう。一般の想像を超える表現。称賛と拒絶こそが物語に天才が必要な理由です。つまり、天才と凡人というコントラストこそが、ヴィヴィットな物語を作るのです。
これが、天才しかいない物語の場合はどうでしょうか。天才しかいない世界にいる天才は、ただの一般人になってしまいます。
二次予選と本選との間にある休日の、天才たちの会話の、なんと空虚なことか。天才たちしか残らなかった舞台は、途端に現実感を失っていきます。今まで紙一重でリアリティをつなぎ留めていたのは、明石という、天才ではない存在があったからだと、今なら分かります。
風間塵というデウス・エクス・マキナ
--遠からぬ将来--あの風間塵を落とした審査員、というレッテルが永遠に残ることになるということだ。
「蜜蜂と遠雷」より
コンクール審査員の1人である嵯峨三枝子(さが みえこ)の三次予選前の独白ですが、これが風間塵の物語での役割を決めています。彼が本選に残ることは、この時決まったのでしょう、また彼が1位をとることが無いのが決まったのもこの時でしょう。
彼は、デウス・エクス・マキナです。
作者の都合の良いように、物語を変えることが出来てしまう、機械仕掛けの神です。
神は、主人公にはなれません。どちらかと言うとラスボスや黒幕です。そんな存在が1位になることは出来ません。そして、彼に共感できてしまう英伝亜夜も、塵と同じ立ち位置にいます。そのため彼女も同じく1位になる必要がありません。
結果として、残った3人の中で唯一、ただの人であったマサルが1位になることは、三次予選前から決まっていました。
序盤、塵という存在はコンクールやクラシックという舞台を揺さぶるモンスターとして表現されていましたが、物語の都合から手なづけられて、ただの天才として周りから評価されて終わってしまいました。思わせぶりだった審査委員長のオルガや塵の存在に嫉妬していたシルヴァーバーグの伏線の回収もありません。
彼の、既存の音楽を破壊するかと言われた「厄災」であった、暴力的なまでの天才性はなりを潜めて、周囲の音を進化させる天使のような「ギフト」だけが残りました。そして周囲もそれを受け止めている。受け止めてしまっています。
”コンクール”というゲーム盤と、”天才”というそのゲーム盤の外側の存在の戦いは、コンクール側の不戦勝となったのです。ここに、コンクールというもののつまらなさを感じたのは僕だけでしょうか。
”音楽コンクールをそのまま、最初から本選までのすべてを小説として書く”という作者の考えを通すために、主人公であった天才たちは、その天才性を失ってしまったのです。